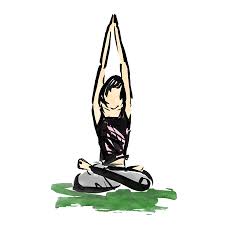プラーナ・ヤーマは、精神的要素と肉体的要素を結ぶ絆である。
この活動は肉体的なものだが、その効果は心を静め、澄ませ、安定させることである。
ヴィシュヌ・デバナンダ
ヨガの呼吸法は、プラーナ・ヤーマと呼ばれます。
プラーナは気やエネルギー、ヤーマはコントロール、エネルギーのコントロールという意味です。
アシュタンガヨガの8支則の4番目にあたります。
プラーナ・ヤーマは、体の活力、精神の安定、明晰な精神を産みだします。
練習は、横隔膜を活用した腹式呼吸から始めましょう。
腹式呼吸から、完全呼吸に進み、ある程度マスターしたら、基本の呼吸法を練習します。
また、プラーナ・ヤーマをするときは、プラーナが流れやすいように、頭と首と背骨が一直線になるように座ります。
そうすると肺の膨らむ空間がとれます。
安楽のポーズか蓮華座で座って行いますが、どちらも楽にできない場合は椅子に座っても構いません。
基本中の基本の呼吸は、腹式呼吸です。
それからとても大切なヨギック・ブリージング(完全呼吸法)へ進みます。
ヨガの腹式呼吸法 やり方
ヨーガのプラーナヤーマは、体の活力、精神の安定を作りだします。
プラーナヤーマの練習に共通しますが、プラーナが全身に流れやすいように、またはいが十分に機能するように、背骨をまっすぐにして、背骨と首と頭が一直線になるようにします。
腹式呼吸はヨーガのプラーナヤーマ(呼吸法)で、最初に覚える呼吸法です。
初心者は腹式呼吸の練習から始めます。
また中級者以上の人でも、たまに腹式呼吸を練習して、きちんとできているか確認が必要です。
まず初めに大切なことは、リラックスして深い呼吸をするということです。
最初はシャバ・アサナで、お腹に片手をおいて、お腹が膨らんだりへこむのを確認しが慣らします。
慣れてきたら、安楽のポーズか半蓮華座、蓮華座で行います。
やり方
*シャバ・アサナになり、十分にリラックスします。
*片手をお腹におきます。
*ゆっくりはいていきます。腹筋を無理ない程度に使いお腹をへこませます。
*吐ききったら、腹筋を緩めて静かに吸います。この時お腹が膨らむのを確認します。
*じょじょに呼吸を深くしていきます。しかし無理な負担を体にかけないように少しずつ行います。
初心者は20回くらいから始めて、じょじょに回数をのばし、慣れてきたら、ヨギック・ブリージングに進みます。
吐く息ではいの下にたまった空気を吐き出してしまいますが、マイナスの感情なども一緒に吐くイメージを持ちます。
吸う息で、肺の下まで新しい新鮮な空気を入れますが、よい考え、新鮮なプラーナを感謝して取り入れるイメージを持ちます。
ヨガの完全呼吸法 やり方
腹式呼吸の次に、ヨーガの完全呼吸(ヨギック・ブリージング)を学びます。
完全呼吸(ヨギック・ブリージング)は、3つの段階で吸い、3つの段階ではきます。
- 腹式呼吸 肺の下に空気を出し入れ
- 胸式呼吸 肺の真ん中の空気を出し入れ
- 鎖骨呼吸 肺の上に空気を出し入れ
この3つをひとつの呼吸で行います。
吐く息
まず、腹式呼吸でお腹をへこませます。
次に、胸式呼吸で胸、特にあばらを縮ませます。
最後に、肩と鎖骨のあたりを下げます。
これを一息で吐きます。
吐く時は、空気をまず肺の下の方から出すようにして、次に真ん中、最後に上から空気をはいていく感じになります。
吸う息
まず、腹式呼吸でお腹を膨らませます。
次に、胸式呼吸で胸とあばらを膨らませます。
最後に、肩が自然に上がるまで吸います。
これを一息で吸います。
吸うときは、肺の下に空気を入れて、次に真ん中、最後に上に順番に空気を入れる感じです。
練習するときは、安楽座か半蓮華座、蓮華座で座り、片手をお腹に、片手を胸にあてて、膨らんだりへこんだりするのを確認しながら行います。
慣れてきたら、吸いきった時に、クンバカ(息を止める 止息)を入れます。
シバナンダヨガの基本の呼吸法
基本の呼吸法は5つあります。
カパラ・バディとアヌローマ・ビローマはとても大切で、基本の部分ですので、これをプラーナ・ヤーマの柱とします。。
まずはこの2つを行ってから、アサナを行います。
カパラ・バディは、肺と内臓を強化し、脳に新鮮な酸素を送ります。
アヌローマ・ビローマはナディ(エネルギーの通り道、経絡のようなもの)の浄化にとても役立つ訓練であり、上級の呼吸法に向けて体の準備を整えてくれます。
カパラバディ やり方
プラーナヤーマは精神的要素と肉体的要素を結ぶ絆である。この活動は肉体的なものだが、その効果は心を沈め、澄ませ、安定させることである。
スワミ・ヴィシュヌデヴァナンダ
カパラ・バディは6つのクリヤ(浄化訓練)のひとつでもあり、同時にプラーナヤーマのひとつでもあります。
このプラーナヤーマはシバナンダヨーガの基本の呼吸法のひとつです。
サンスクリット語でカパラは頭、バディは輝くという意。
吐く時に強く吐き、肺の酸素を一気に押し出します。
そのあと、力を抜くと自動的にはいに酸素が入ってきます。
このポンピング、をレベルにもよりますが20回程度繰り返します。
初心者は10回くらいから始めましょう。
何度か繰り返した後、大きく吸って息を止めます(クンバカ)。
これが1ラウンドで3ラウンドから5ラウンド繰り返します。
吐く時は積極的に一気に吐く。
吸うときは受動的に自然に息が入ってくるという感じです。
カパラバディのポイント
*腹筋を素早く収縮させ、横隔膜を上に押し上げてはいから強く吐き出す
*腹筋を緩めて、横隔膜を下に自然に下がるようにする。意識的に吸うのではなく、自然に息が入ってくる。
*空気の通り道、肺、呼吸器系全体が浄化されてきます。
*赤血球がより多くの酸素を吸収するようになり、血液が浄化されます。
*脳に新鮮な酸素が大量に送られ、脳が活性化します。
*腹筋が強化され、消化機能が高まります。
*便秘に特効があります。
*太陽神経叢にプラーナ(エネルギー)をチャージします。
*こころをリフレッシュさせ、活力を与えますので、ポジティブ・シンキングに役立ちます。
カパラバディの注意点
妊娠中はこの呼吸法はできません。
ぜんそくの方にとても良い呼吸法ですが、ぜんそくの発作の時はしてはいけません。
ヨガの片鼻呼吸法 アヌローマ・ビローマ やり方
プラナヤマ(呼吸法)は精神と肉体の規律をつなげ、肉体が行動をしている間、マインドを沈め、明晰に、そして安定させる効果を発揮する。
ヴィシュヌ・デヴァナンダ
呼吸が乱れているとき、心もまた安定しない。
呼吸が安定しているとき、心もまた安定している。
ヨーギは長く生きる。だから呼吸を止めているべきである。
ハタヨガ・プラティピカ 2章2節
アヌローマ・ビローマという片鼻の呼吸は基本の2つの呼吸の1つです。
1 右手の中指と人差し指を折り曲げ(ヴィシュヌ・ムドラ)鼻のところに持ってきます。
2 両方の鼻から大きく息を吐き出します。
3 親指で右をふさぎ、左から吸います。
4 左を薬指と小指で閉じます。両方閉じた状態です。これをクンバカといいます。
5 左を閉じたまま、親指を離し右から吐きます。
6 同じ右からすいます。
7 親指で右を閉じます。両方閉じたクンバカの状態。
8 左だけ離し、左から吐きます。
9 左から吸います。
この繰り返し。
腹式呼吸の要領で、最初は吸う、吐く、止めるを同じカウントで行い、慣れてきたら、1対2対4の割合で行います。
吸う4カウント、吐く8カウント、止める16カウントなど。
5セットくらいから始めるとよいでしょう。
この呼吸はカパラ・バディのすぐ後に行います。
陰と陽の呼吸とも呼ばれる
右が陽で太陽、活力、ピンガラを象徴しています。
左が陰で月の、癒し、イダーの要素。
私たちはどちらかから多く呼吸していて、健康な場合、3時間くらいで自然に入れ替えています。
心身の不調が続くとそれが乱れてきます。
右鼻は左の背筋のところにある交感神経と関係していて、左は右の背筋の副交感神経とつながりがあります。
うつ、神経の乱れ、自律神経の乱れなどに特効があります。
片鼻呼吸の効果
*肺と呼吸器全体が浄化され、強化されます。
*吐くを数の2倍の長さにすることで、よどんだ空気や老廃物を肺からよく吐き出せるような体になります。
*右は熱、太陽、異化作用(分解作用)と内臓の活動を促進させます。左は、冷たさ、月を表し、同化作用と体を静かにさせます。この2つの対極のエネルギーのバランスをとるのを助けます。
*アヌローマ・ビローマは右脳と左脳のバランスもとります。
*体を軽くし、目を輝かせます。
*心を安定させ、瞑想の準備になります。
*ナディ(経絡、エネルギーの通り道)を浄化します。
ブラフマリ、シートゥカーリー、シータリーは、重要度の低いプラーナ・ヤーマですので、時間のゆとりのある時に行えばよいでしょう。
プラーナ・ヤーマの練習で特に大切なことは、いろいろな呼吸法を覚えることではなく、基本の2つをじっくりと、完全にできるようにすることです。
上達とは、呼吸をじょじょに、深く長くするようにすることと、エネルギーの流れを意識することです。
自律神経の不調や、やる気が出ない、落ち着かないなどはプラーナ・ヤーマの定期的な練習で、比較的簡単に改善できます。
また肥満や体調不良にもとても大きな効果があります。